
副業が当たり前の時代になりつつある?
こんにちは。Vmaster税理士事務所代表者の松田光弘です。これは様々なお客様からのご相談対応をしている中で感じた個人的な印象ですが、近年、会社員の副業がますます進んでいるように思います。
実際に、ソフトバンクやリクルートなどの大企業をはじめとして従業員の副業を認める会社も増えてきています。この背景には賃上げ圧力やリスキリングの奨励という風潮が強まってきていることがあると思われます。本稿では副業を行うにあたって税制及び社会保険制度の側面から副業のメリットと注意点を述べたいと思います。
副業のメリットと注意点
税制面のメリットと注意点
副業で税制面のメリットを得るには専門家の協力が必要になります。まず、基本的に給与所得は「給与所得控除」によって他の所得よりも税制面で優遇されています。以下の表のように、本業の給与収入が500万円あった場合には給与所得控除が144万円となり、給与所得は差引356万円になります。
| 給与収入金額(A) | 給与所得額(B) | 控除率((A-B)/A) |
| 50万円 | 0円 | 100% |
| 100万円 | 45万円 | 55% |
| 200万円 | 132万円 | 34% |
| 300万円 | 202万円 | 33% |
| 400万円 | 276万円 | 31% |
| 500万円 | 356万円 | 29% |
| 600万円 | 436万円 | 27% |
| 700万円 | 520万円 | 26% |
| 800万円 | 610万円 | 24% |
| 900万円 | 705万円 | 22% |
| 1,000万円 | 805万円 | 20% |
この356万円が所得税と住民税の課税標準(税額を計算する基準の金額)となりますから、この場合には給与収入の約3割は無条件に免税されていると言えるわけです(免税という表現は正確ではないですが、分かりやすくするためにあえて使っています)。
一方、事業所得や(事業として認められる規模の)不動産所得に関しては一定の条件のもと青色申告特別控除が使えますがその控除額は65万円でありますから、事業収入が500万円の場合には控除率は65/500=13%となり、免税される割合は給与収入の約3割に対して1割強と比較的小さくなってしまいます。しかも青色申告特別控除を使うためには複式簿記で取引を記帳しなければならず、そのために必要な会計ソフトの使用料などもかかってきますので、実際の割合はこれよりもさらに小さくなり、事務負担も増えます。また、個人事業税の対象となる事業も多くありますので、その対象であれば年290万円の控除後の所得金額に対して3%~5%の税率で事業税が生じることも重要です。
したがって、事業所得の控除率を高めるためには、いかに事業所得を小さく収めるかの知見が必要になります。それは一般に「経費で落とす」と言われますが、当然、事業に必要な支出しか「経費で落とす」ことはできません。ところが、この事業に必要な支出かどうかというのが明確に分けられる場合と、そうでない場合が混在しているのが現実です。
この現実に対して、意外なことに所得税法では「必要経費に算入できる金額は、売上原価その他事業収入を得るために直接要した費用の額と販売費・一般管理費その他業務上の費用の額です」とか「家事上の経費は必要経費に算入しません」とか大まかな規定しかありません。
もちろん、国税庁は個々の経費の取り扱いに関して基本通達(こういうときはこう判断してくださいね、という国税職員用のマニュアル)を開示していますが、通達は法源(法と認められるもの)に当たらないので、個々の経費の取り扱いに関しては税務署と納税者が揉めやすいポイントになります。
そこで、税法の専門家である税理士が様々な学者による法解釈や判例(最高裁判所の裁判例)に基づいてセーフとアウトのラインを判断する必要があるわけです。税理士は単なる申告代理人ではなく、税法解釈と実務判断の専門家です(残念ながらそこを分かっていない税理士も散見されますが、これ以上言うと税理士法に触れるので控えます)。
話が脱線しましたが、つまり、事業所得の控除割合は小さいので、必要経費を増やさないと所得税や住民税の面で不利になります。そして必要経費にできる、できないの判断は法制度に関する専門的な知識を要しますから、税理士に聞いたほうが安全です。
税務署は一般の方々が思っている以上にあらゆる情報を掌握しており、国内に口座や財産を置いている方なら収入が急に増えたり大きな資産を保有したりすれば直ぐに分かります。全ての納税者から適法に税を徴収することが税務当局の任務なので、彼らは脱税や申告漏れに対しては調査にコストがかかろうが何だろうが必ず追い詰めてきます。事業を行う方々はそのあたりの認識をきちんと持つことが重要でしょう。
社会保険制度面のメリットと注意点
社会保険制度に関しては社会保険労務士の専門範囲ですからここで深い知見を提示することは難しいのですが、現行の制度下では本業で会社から給与収入を得て健康保険と厚生年金に入っていれば、個人事業主として副業をしている場合のその副業に関しては社会保険に入らなくて済みます。
つまり、同じ会社員でも年収800万円の人(A)と、年収400万円+副業(個人事業)収入400万円の人(B)とでは社会保険料が倍近く違ってくることもあり得ます(詳しい計算は地域や健康保険組合により異なります)。余談ですが、個人事業主は国民健康保険の高さが悩みの種と言われます。そこで中にはこの仕組みをうまく使って、ひとり法人を作って少額の役員報酬をもらい、その法人で社会保険に入ることで社会保険料を抑えるスキームを実行している事業主もいます。
つまり、副業は社会保険料を抑制する効果があると言えるでしょう。ただ、このような抑制が可能なのは制度の未整備によるものとも言えますから、長い目で見れば法改正により是正されていくかもしれません。
また、会社が社会保険料の負担を軽くするために、実態は従業員と変わらないにも関わらず業務委託形態を偽装して、従業員を個人事業主の扱いにするような事例も散見されるようになってきています(いわゆる「偽装請負」)。業務委託を行う場合には、労働者性がなく個人事業主としての実態があるかどうかを契約書と業務体制の両方で担保する必要があります。このあたりは労働基準法の範疇なので私の専門外ではありますが、以下の「労働基準法における「労働者」とは」(厚生労働省)のページが参考になるでしょう。
もし個人事業主でなく労働者であると認められてしまった場合、個人側は社会保険料や源泉所得税を会社から徴収されたり、所得税の修正申告(必要経費がすべて認められなくなる)をしなければならなくなったりなど大きな負担が生じますし、会社側も社会保険料の徴収・納付や源泉所得税の徴収・納付、加算税の納付などさらに大きな負担が生じます。したがって、個人との業務委託契約に関しては労働者性を排除するためにも社会保険労務士などの専門家を交えて慎重に確認することが必要と言えるでしょう。
終わりに
現行の法制度は副業の普及など働き方が多様化する流れに追い付いていないというのが現実です。しかし、副業は税制面や社会保険制度面のメリットだけでなく、自身のスキルアップや視野と見識を広めることにもつながりますので、個人的な意見としては(本業の仕事を一部他の人に任せるなどして)時間を割いてでもやるべきだと思います。新しく副業を始めてみたい、という方はぜひ弊事務所までご相談ください。手取り計算のシミュレーションから必要経費の組み立て、その後の継続的な事業展開のご相談まで手厚くご支援いたします。
※ 本稿に掲載されている情報は、2025年6月7日時点の法制度に則って一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の事案に対する税務判断を示すものではありません。最新情報の提供や個別の状況への対応については税務署や税理士等にご相談ください。弊事務所では個別相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせページからご連絡ください。

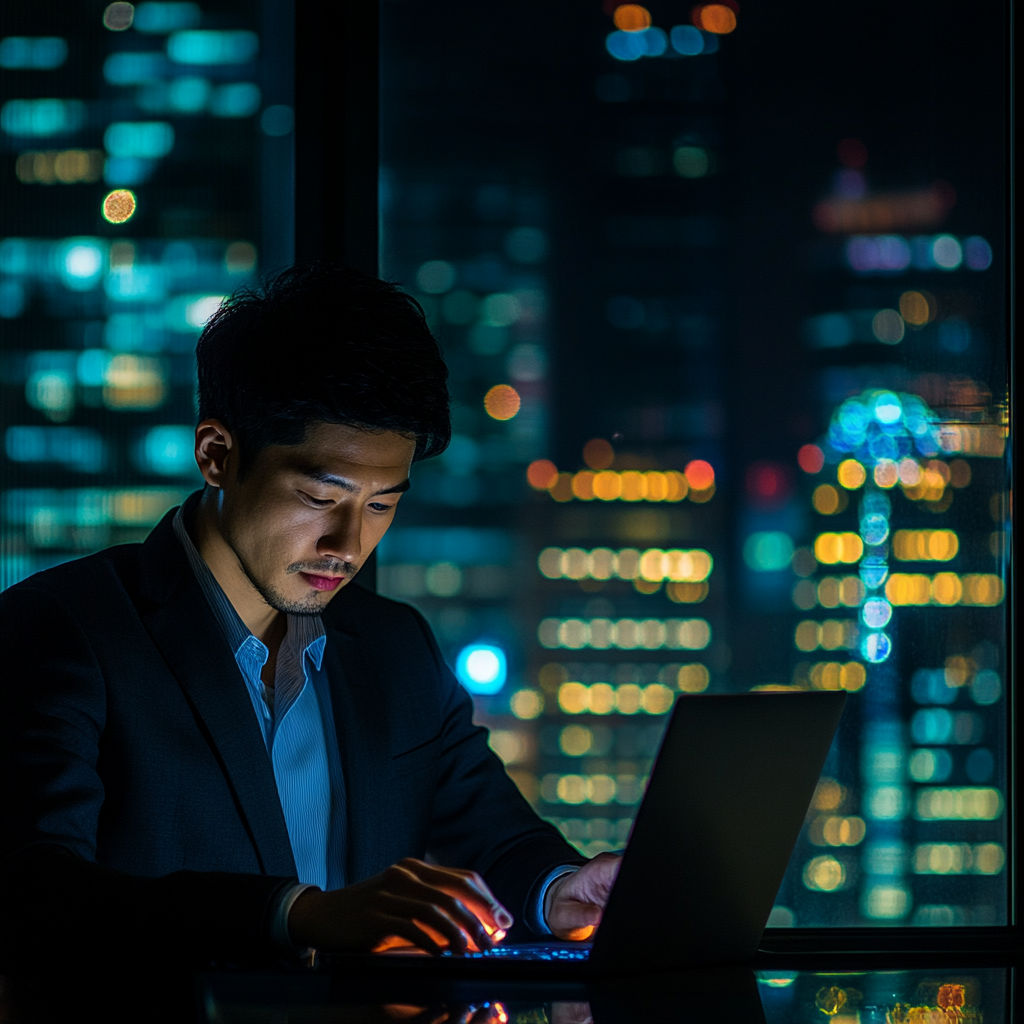


コメント